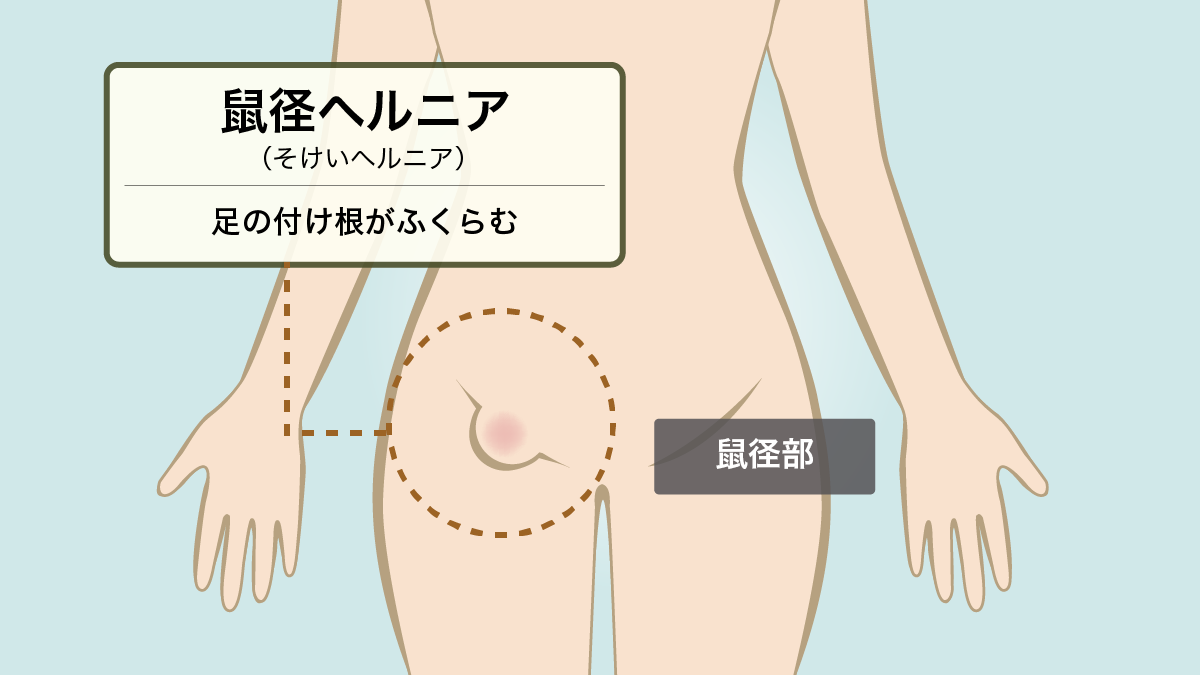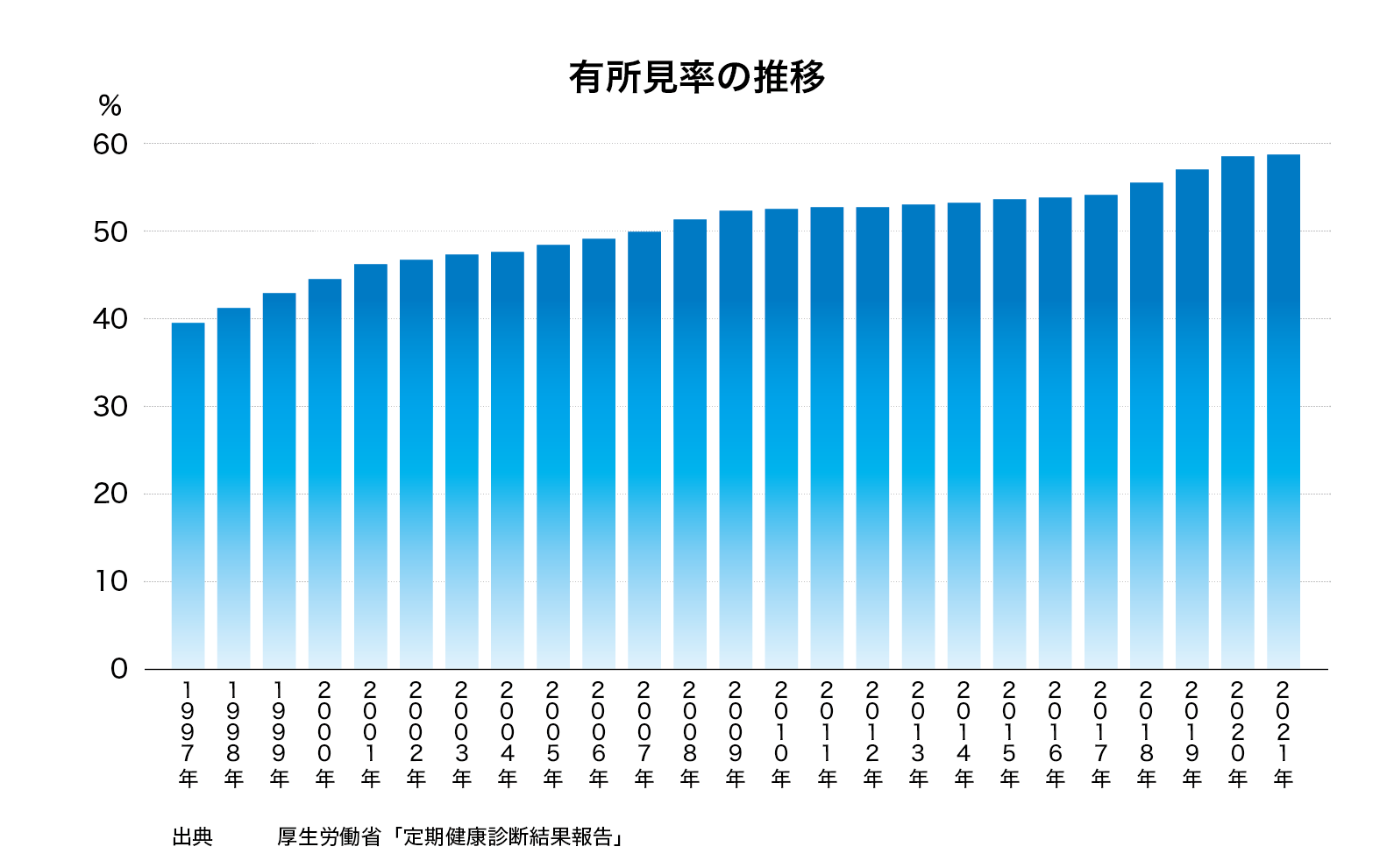臨床診断研究センター 医師 加藤 開一郎
暑さもひと段落し、心地よい気候の季節となってきました。本来ならば快適な秋ですが、夏から冬への季節の変わり目は、人によっては精神的に不安定になりやすい時期でもあります。
最近、何となく体が重たい、やる気が出ない、食欲がない、寝つきが悪い・・・そんな夏の後半から始まる体調不良や気分の変化は、季節性うつ病の可能性も考慮する必要があります。
このような特定の季節にだけ、気分の落ち込みなどのうつ症状がみられる疾患を季節性うつ病と言い、季節性情動障害とも呼びます。季節性うつ病は、秋から冬にかけて発症することが多く、冬季うつ病ともいわれ、冬を越えて春になる頃には自然回復する傾向があります。
季節と気分情緒の関係
哺乳類は進化の過程で、外部環境の季節的変化に適応するため、体の生理機能や行動を変化させる「光周性」という仕組みを獲得してきました。これは、太陽の出ている時間の長さから、季節の変化を無意識に把握し、情動・社会行動・睡眠・食欲・体重に影響を与えるとされます。人類にもその名残が存在するとされ、例えば「食欲の秋」という言葉がありますが、これは「食物が乏しくなる冬に備えて体に栄養を蓄える」、そんな哺乳類としての本能が人に残っていることを表しているのかもしれません。
さまざまな身体症状で受診することも
近年、一般に知られるようになってきた季節性うつ病ですが、必ずしも気分の落ち込みで発症するわけではありません。うつ症状よりも「食欲がない」「体がだるい」「眠れない」「不安で仕方ない」など、気分の落ち込み以外に、消化器症状や倦怠感、不安焦燥感、睡眠障害の症状が全面に出る方が多い印象です。自分は良くない病気なのではと心配され内科を受診される方もいます。しかし、問診を通じて、過去にも同じ時期に似た症状を経験していたことが判明することがあり、季節性うつ病を疑うきっかけになります。
うつ病を「心の病気」から「脳の病気」と捉えなおす
季節性うつ病に限らず、うつ病やうつ状態の原因には、脳内の神経伝達物質の不足が大きく関与しています。筆者はうつ病やうつ状態は「心の病気」ではなく「脳の病気」と捉えるべきと考えています。何故なら、うつ病やうつ状態を「心の病気」ではなく「脳の病気」であると捉えなおすと、治療の考え方の本質が変わり、「心の状態を治す」のではなく、「脳を治す=脳の神経細胞やその機能を回復させる」と発想が変わります。
栄養状態の改善が治療の第一歩
うつ病は神経伝達物質の枯渇が原因ゆえに、うつ病の治療には抗うつ薬と呼ばれる、神経伝達物質を間接的に増やす薬剤が使用されることが多くあります。しかし、筆者はうつ病治療には、薬物治療や精神治療に先んじて栄養状態の改善が大切だと考えています。これは脳の回復に必要な物質をしっかり届けることが、何よりも最初にすべき治療だと考えるからです。栄養の中でも重要と考えるのが、神経伝達物質の材料となるタンパク質をしっかり摂取することが最も重要と考えています。栄養が不十分で神経伝達物質の原料が枯渇した状況での薬物治療は、ガソリンの入っていない自動車のアクセルを踏むようなものです。
食欲低下への対処法
しかし、うつ病になると、多くの方が食欲の低下を自覚します。筆者はそのような方に対し、「とにかく良質な動物性タンパク質だけは、どんな調理形態でもいいので、頑張って召し上がってください」とアドバイスし、抗うつ薬ではなく、消化器系の治療薬で食欲改善を第一にすることもあります。それは、うつ病は「脳の病気」であり、その脳の神経細胞やその機能が修復されためには何が必要かということを考えるからです。そして、栄養そのものがうつ病状態にとって最も大切な「薬」だと考えるからです。もちろん、タンパク質だけではなく、ビタミン、ミネラルも正常な細胞の活動には必須ですので、これも忘れず摂取していただくようにお話ししています。抗うつ薬は胃の不快症状をきたすことがあり、時としてもともと悪化傾向だった栄養状態をさらに悪化させてしまう可能性すらあり注意が必要です。
自己認識と予防の重要性
季節性うつ病において、自分はその傾向にあるかもしれないと自己認識できることは、翌年の同じ季節に同様の症状の深刻化を回避するのに重要だと思います。それは、症状が出やすい時期に備えて、肉・卵・牛乳を意識して摂取することで、症状の軽減や予防につながります。栄養状態の改善によってうつ症状の改善または予防を図っています。
「毎年のいつもの症状が始まったかもしれない」と感じた段階から、あるいは少し前から意識的に栄養を整えることが、季節性うつ病への対策となるのではと考えます。
【参考引用文献】
様々なタンパク質源摂取による冬季うつ病の予防改善効果の解析
浦上財団研究報告書 22 (2015) P49-55
薬に頼らずうつを治す方法.藤川徳美著.アチーブメント出版
アミノ酸・タンパク質を基点に心と脳の健康を考える.日本食生活学会雑誌33巻4号P179-184.2022