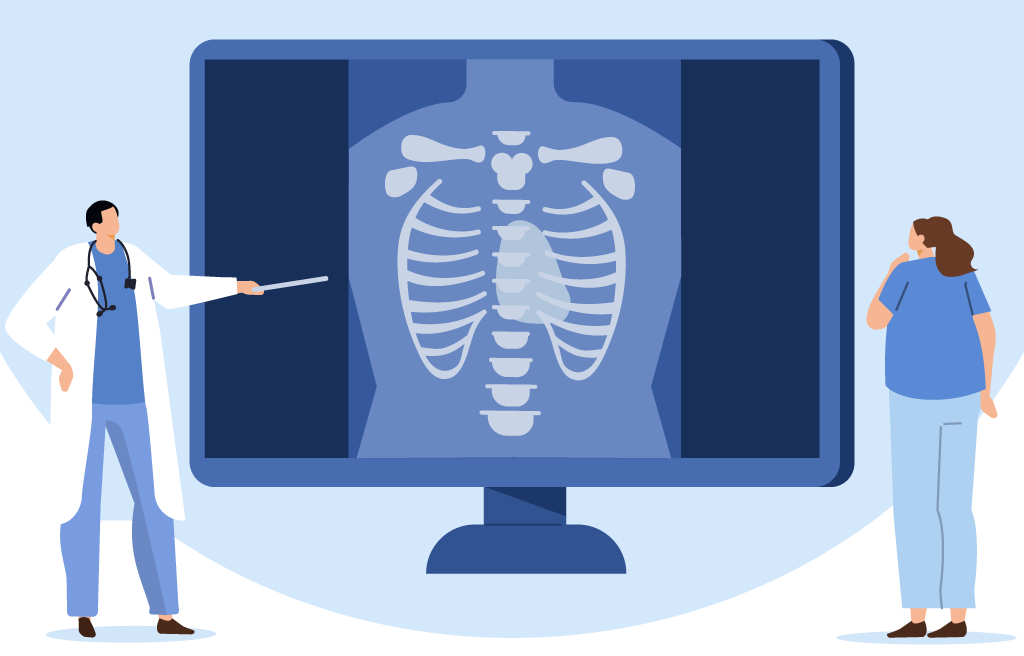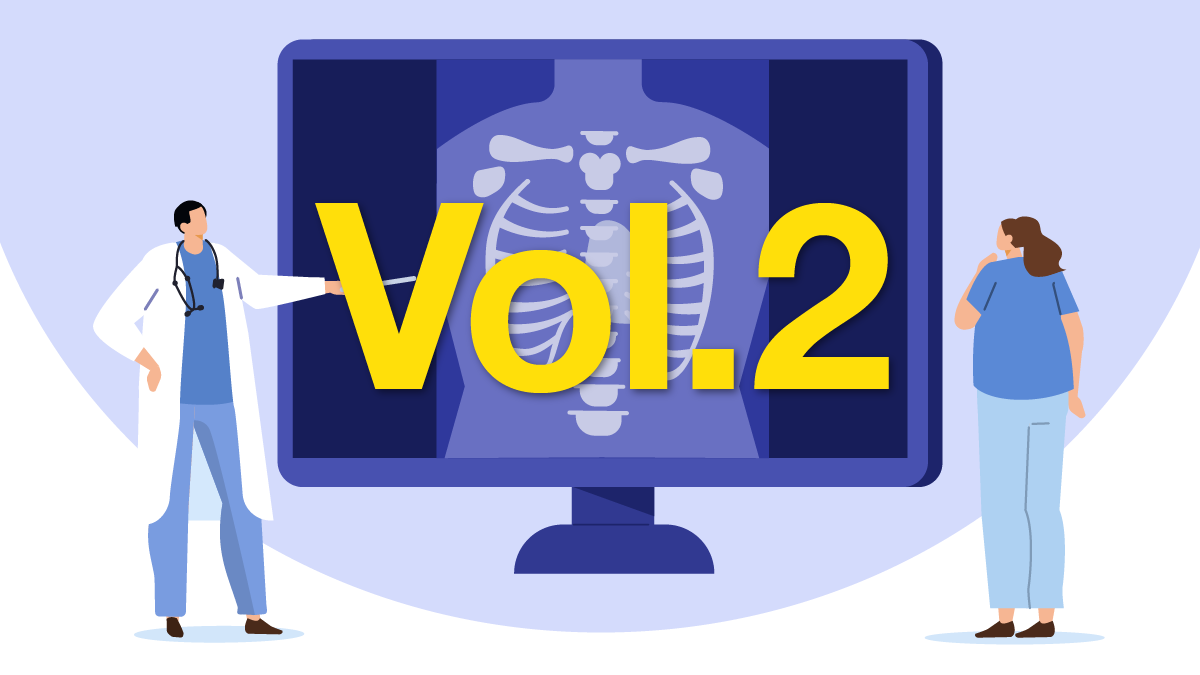―非糖尿病者の低血糖の原因とは
医師 加藤 開一郎
はじめに
従来、低血糖を来す疾患は比較的稀であると言われてきました。しかし、近年の非糖尿病者の低血糖の報告が増加しています。その中には慢性的な低血糖症状を、うつ病や認知症と誤診されていたケースの報告も少なくありません。
インターネットには、糖尿病治療に関連する低血糖の情報は、豊富にみられます。その一方、非糖尿病者の低血糖について詳述した情報は、非常に限られ、またその多くが断片的な情報です。このため、本コラムでは、「非糖尿病者の低血糖の原因」をテーマに非糖尿病者の低血糖について、より系統的に詳しく説明し、低血糖への理解を深めていただきたいと思います。なお、今回のコラムは、成人非糖尿病者の低血糖を想定したお話なので、糖尿病治療薬による低血糖、および小児の先天性代謝異常に伴う低血糖には触れていないことを予めご了承ください。
低血糖が生じる原因メカニズムとは
健康な人でも食事をしてしばらく時間が経過すると空腹を感じます。これは生理的な血糖変動です。しかし、通常のカロリーの食事を摂取し、身体活動量も極端に多くないのに、生理的な血糖変動の範囲を超え、病的な血糖の低下を来すことがあります。本コラムではこのような血糖の低下を「低血糖」と呼称し解説していきます。
早速、低血糖の原因疾患を見ていきたいと思います。表1に低血糖の原因を列挙しました。聞きなれない病名ばかりだと思いますので、1つずつ後述していきます。
表1.低血糖の原因分類
――――――――――――――――――――――――
■内因性低血糖
インスリノーマ
膵外腫瘍
非インスリノーマ性低血糖症候群
・反応性低血糖(食後低血糖症)
・上部消化管術後低血糖症(胃切除・幽門側胃切除・肥満手術)
・成人膵頭細胞症
自己免疫性低血糖
・インスリン自己免疫症候群
・インスリン受容体異常症B型
インスリン拮抗ホルモン低下症
・下垂体前葉機能不全症
・副腎皮質機能不全症
重症腎不全
肝硬変・肝不全
低栄養(例:神経性食思不振症)
■外因性低血糖
・薬剤性低血糖(血糖降下薬・インスリン)
・薬剤性低血糖(糖尿病治療薬以外の薬剤)
・アルコール性低血糖
・運動後遅発性低血糖
―――――――――――――――――――――――――――――――
上記の表をご覧いただくと、低血糖には、かなりの種類があることがお分かりいただけると思います。低血糖は大きく内因性低血糖と外因性低血糖に分類できます。内因性低血糖は、自身の身体の中の原因による低血糖です。これに対し、外因性低血糖は、薬剤やアルコール、過度な運動、インスリン注射など、体外からの低血糖を誘発する原因が存在する低血糖をいいます。ここからは、上記の表に列挙した疾患について詳細を説明していきます。
■インスリノーマ
インスリノーマは、インスリンによる低血糖を引き起こす代表的な疾患の1つです。インスリンは膵臓のβ細胞でつくられるホルモンの一種で、血糖を下げる作用があります。インスリノーマは、このインスリンを産生する細胞が腫瘍性に増殖し、血液中のインスリン濃度が上昇するため低血糖を来します。
■膵外腫瘍による低血糖
インスリノーマは膵臓にみられる腫瘍ですが、まれに膵臓以外の場所の腫瘍性病変が、インスリンに類似した成分を分泌することがあり、この成分による低血糖が生じることがあります。これを膵外腫瘍による低血糖と呼んでいます。
■反応性低血糖(食後低血糖症)
反応性低血糖は食後低血糖症とも呼ばれ、食事による急激な血糖上昇に対し、過剰にインスリンが分泌されることで生じる低血糖です。食後に気分不快、異常な眠気、倦怠感、頭痛、動悸等の低血糖症状が見られる場合、反応性低血糖の可能性を想定する必要があります。
■上部消化管術後低血糖
胃切除後や幽門側胃切除の手術を受けたことがある方に見られる低血糖です。胃の手術後は、急速に食物が小腸に流れ込むようになり、急激な血糖上昇につながります。これにより急速に過剰なインスリンが分泌され、低血糖を生じます。低血糖症状の出現は、食後2~3時間が多く、冷や汗、めまい、空腹感、倦怠感などの低血糖症状を来します。
また、近年は高度肥満の方に対する、肥満手術が国内でも実施されるようになっています。この肥満手術の術後の方に低血糖が生じることが報告されています。この原因として、高度肥満の方は、術前にインスリン抵抗性と呼ばれるインスリンの効果減弱があるため、大量のインスリン分泌の状態にあります。このため、肥満手術後にもこれまで同様のインスリンが分泌さると、相対的にインスリンが過剰となり、低血糖を生じる原因の1つであると推測します。
■成人膵頭細胞症
膵頭細胞症は、小児では先天性高インスリン血症とも呼ばれ、成人膵頭細胞症は成人で発症、発見される高インスリン血症による低血糖です。先述したインスリノーマも高インスリン血症を来す膵臓疾患ですが、膵頭細胞症は、膵臓のβ細胞が腫瘍は形成せずに、過剰にインスリンを分泌するため低血糖を来します。
■インスリン自己免疫症候群
自己免疫性低血糖の1つで、免疫のトラブルで自分自身の膵臓から分泌されるインスリンに対し、自己抗体をつく疾患です。インスリンと抗体が結合した状態から、急激にインスリンと抗体が離れ、そのインスリンがインスリン受容体に作用すると低血糖を引き起こします。
■インスリン受容体異常症B型
これも自己免疫性低血糖の1つです。インスリン受容体に対し、誤って自己抗体ができてしまい、インスリンとインスリン受容体間の作用を阻害します。このため、夜間・早朝に低血糖を来し、食後には顕著な高血糖を呈します。何らかの自己免疫疾患を有している方に発症しやすいとされています。
■下垂体前葉機能不全症
下垂体前葉には、インスリン拮抗ホルモンと呼ばれる血糖を上昇させるホルモンの分泌をコントロールする機能があります。下垂体前葉の脳梗塞、脳出血、腫瘍、炎症などのトラブルにより、下垂体前葉が正常に機能できなくなると、副腎からの血糖を上昇させるホルモンの分泌が低下し、低血糖を来します。
■副腎皮質機能不全症
副腎皮質はコルチコイドと呼ばれるホルモンを産生する臓器で、血糖については副腎皮質で産生される糖質コルチコイドが血糖の維持に関与します。副腎皮質機能が低下した状態では、糖質コルチコイドの産生分泌が低下しますので、低血糖が生じます。
■肝硬変・肝不全
肝臓は血糖の維持に2つの大きな役割を果たします。1つはブドウ糖をグリコーゲンとして貯蔵する役割です。もう1つは非炭水化物系の栄養からブドウ糖を生み出す「糖新生」の役割です。私たちが食事を抜いても、急に低血糖で倒れないで済むのは、肝臓に蓄えられた糖質の放出や糖新生により、血中のブドウ糖濃度が維持されるためです。
しかし、肝硬変や肝不全の状況では、まずブドウ糖の貯蔵庫としての役割が果たせなくなります。さらに肝硬変では糖新生の働きも低下しますので、低血糖を来しやすくなります。その上、肝臓におけるインスリンの分解も遅くなりますので、さらに低血糖を来しやすくなります。このため、肝硬変を持病でお持ちの方は、低血糖に注意が必要になります。
■アルコール性低血糖
アルコールは肝硬変の原因の1つで、肝硬変を介して低血糖を来しますが、肝硬変を来していない状況においても、アルコールの多飲自体が肝臓における糖新生を阻害し、低血糖を来す原因となります。このため、アルコールの多飲の方が意識障害を来した場合には、アルコール中毒だけではなく、低血糖による意識障害も想定しておく必要があります。
■重症腎不全
腎機能が高度に低下し、維持透析を開始した方は、低血糖がみられることがあります。この原因は3つあります。1つは腎機能の低下によりインスリンの分解が遅くなることです。これにより血中のインスリンが高めに残存し、低血糖につながりやすくなります。2つめに腎臓は肝臓と同様に糖新生の働きを担う臓器です。腎機能が低下した状態では、この糖新生の機能が低下しており、低血糖につながりやすくなります。さらに血液透析自体でも低血糖が生じる場合があり、透析をされている方は、低血糖には注意が必要です。
■医原性低血糖(糖尿病治療薬・その他薬剤)
糖尿病治療で使用される血糖降下薬・インスリンは、低血糖の原因となることは多くの方が認識されていると思います。しかし、糖尿病治療以外の薬剤も低血糖の原因となることがあり、プロポキシフェン、β ブロッカー、サルファ剤、サリチル酸、ジソピラミド抗不整脈薬のシベンゾリン、抗菌薬の一種であるペンタミジンは低血糖の原因薬剤として知られています。このため、低血糖を指摘されたら、糖尿病治療を受けていなくても、薬剤をきちんと確認する必要があります。
また、医療行為にかかわる低血糖の1つに副腎ステロイドがあります。副腎ステロイド製剤の長期間使用は、副腎からのホルモン分泌を低下させます。この状態で急にステロイドの内服を中止すると、急激な副腎ホルモンの不足を招きます。これはステロイド離脱症候群と呼ばれ、その症状の1つに低血糖があります。このため自己判断によるステロイドの急な中止は絶対に避けなければいけません。
■外来性インスリンによるインスリン抗体が原因の低血糖
膵臓が分泌する本来のインスリンを内因性インスリンと呼ぶのに対し、インスリン注射で使用されるインスリンを外来性インスリンと呼ぶことがあります。インスリン自己免疫症候群のところで、自分のインスリンに対し自己抗体ができることがあるとお話しましたが、インスリン注射をしていると、そのインスリンに対しても抗体ができることがあります。これによりインスリン注射の効果が不十分になり、血糖の変動幅が大きくなり低血糖を来すことがあります。
■運動後遅発性低血糖
激しい運動をして半日ほど経過して低血糖を来すことがあり、運動後遅発性低血糖と呼ばれています。1型糖尿病の患者さんにより多くみられると報告されています。
ここまで低血糖の原因疾患やリスクについて、概説してきました。低血糖の原因疾患を詳細に覚えていただく必要はありません。今回のコラムでお伝えしたかったのは、低血糖の原因は多数に及ぶということです。そして、ご自身の持病や過去の手術歴から、低血糖のリスクがあるかどうかを把握いただければ幸いです。
大切なのは低血糖の症状を知り、疑うこと
今回は2回のコラムで低血糖について解説してきました。何らかの体調不良があったとき、「低血糖の可能性は」と疑うことが重要です。そのためには、低血糖の症状は十分に知っておく必要があります。このため、前回のコラムでご説明した低血糖の症状を表2に再掲します。
低血糖の診療において問診から得られる情報は非常に重要です。特に一定のタイミングで繰り返し生じる低血糖症状は、その時間帯に本当に低血糖を起こしている可能性が高いです。低血糖の症状の多くは、空腹時に生じやすいものが多くを占めます。しかし、反応性低血糖のように食後に限って低血糖の症状が出現する場合もあります。また、空腹時の低血糖でも、夜間や早朝の低血糖なのか、日中の食事の合間の低血糖なのかなど、どのタイミングで症状が出現するかも、低血糖の原因を特定するために重要な情報となります。
長文となりましたが、ここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。
表2. 低血糖時の症状と所見 (実臨床で遭遇する所見)
| 全身症状 | 脱力感 空腹時の倦怠感 ふらつき(特に空腹時) 易疲労感(疲れやすい) |
| 頭部周囲の症状 | 頭痛 めまい(特に空腹時) 生あくび 眠気(空腹時あるいは食後) |
| 眼・視覚 | 霧視(目のかすみ) 瞳孔散大(瞳孔が大きく開いている) 一過性の視力障害 眼振 複視(物が二重に見える) |
| 循環器症状 | 動悸(ドキドキする) 頻脈(脈が速い) |
| 皮膚症状 | 冷や汗 発汗亢進 空腹時の冷や汗 冷感 |
| 顔面 | 顔面蒼白・顔色不良 |
| 消化器症状 | 強い空腹感 飢餓感 吐き気 |
| 手・指 | 手や手指のふるえ |
| 意識・行動 | 意識障害 空腹時の意識障害 意識消失 傾眠傾向 昏睡状態 異常な行動 意味不明な言動 |
| 精神症状 | 抑うつ・うつ状態 無気力、意欲低下 不安・不安感 焦燥感 不穏、錯乱、興奮 せん妄 パニック発作 神経質、易刺激性 |
| 思考・記憶 | 集中力低下 思考力低下 記憶障害 記憶力低下 認知機能低下 |
| けいれん | けいれん発作・けいれん重責 |
| 運動障害 | 体動困難(うごけない) 動作緩慢(動作がゆっくり) 半身麻痺(半身が脱力) 四肢麻痺(四肢が脱力) 下肢脱力感 空腹時の脱力感 失調(体のふらつき) |
| 言語障害 | 呂律緩慢(構音障害) 失語症 発語困難 |
| 感覚障害 | 口唇のしびれ 手足のしびれ |
※筆者に調べ(国内論文のみ)
※本表には軽度低血糖から重度低血糖の症状所見を含む
【引用参考文献】
IGF-II 産生腫瘍と低血糖.糖尿病 54(12):886~887,2011
腎疾患と糖代謝.日腎会誌 2019;61(5):560‒56
HLA-DRB1*04:04 を有した高齢インスリン自己免疫症候群 (平田病)の 1 例
糖尿病 65(6):312~318,2022
肥満手術後に食後低血糖症状をきたした高度肥満を伴う2型糖尿病の 1 例
糖尿病 56(12):943~948,2013
2型糖尿病の経過中に高インスリン血症性低血糖を繰り返した膵島細胞症の1例
糖尿病 67(4):181~188,2024
インスリン抗体により引き起こされる低血糖.月刊糖尿病 #129 Vol.13 No.1 P75
我が国の内因性高インスリン性低血糖症の疫学、診療実態に関する研究
厚生労働科学研究費補助金(難治性疾患政策研究事業) 分担研究報告書
インクレチン分泌動態を検討した成人発症膵島細胞症の 1 例
糖尿病 58(9):695~701,2015
糖尿病治療に関連した重症低血糖の調査委員会報告.糖尿病学会60巻12号P826-842.2017
救急外来における低血糖症例の検討.日本救急医学会雑誌24巻7号P391-398.2013
低血糖性昏睡.日本内科学会雑誌105巻4号P683-689.2016
高血糖緊急症・低血糖.日本内科学会雑誌101巻7号P2085-2090.2012
中枢神経系の後遺症を残した低血糖昏睡3例の臨床像.糖尿病49巻4号P267-273.2006
低血糖昏睡.日本内科学会雑誌93巻8号P1525-1531. 2004
下垂体機能低下症.日本内分泌学会雑誌98巻S.HPT号.P90-92. 2022
心易疲労感・食欲不振などの症状からうつ病を疑われ紹介となったACTH単独欠損症の1例.心身医学55巻3号P261-268. 2015
うつ病とされてきた慢性副腎皮質機能低下症の1例.日本プライマリ・ケア連合学会誌37巻3号P265-267. 2014
うつ病が疑われ心療内科に紹介された下垂体性副腎皮質機能低下症3例の特徴.心身医学56巻11号P1134-1139. 2016
頻回の低血糖発作により判明した維持透析患者の続発性副腎不全の1例.高知赤十字病院医学雑誌.27巻1号P119-122. 2022